独習! フローチャート式デジタル脳波判読法
販売価格: 7,480円(税込)
商品詳細
わかりにくい脳波判読をフローチャート式で、わかりやすくレクチャー!
【目次】
はじめに
略語一覧
第1章 総論
脳波と画像の関係
脳波の基本的知識
I.脳波の発生機序
II.正常脳波
脳波の導出法
I.電極の配置
II.電位の検出
III.導出法と電位分布
IV.脳波判読でよく使われる用語
V.脳波判読を始める前に
VI.具体的なマッピングのやり方
脳波の賦活法
I.種々の賦活法
II.過呼吸(hyperventilation)
III.光刺激(photic stimulation)
IV.音刺激
V.痛み刺激
VI.睡眠賦活(sleep activation)
睡眠脳波
I.成人の睡眠脳波
II.第1期(入眠期、N1)
III.第2期(軽睡眠期、N2)
IV.第3期、第4期(深睡眠期、N3)
V.レム(REM)睡眠
第2章 各論
背景活動の判読
I.背景活動の判読
II.意識障害や覚醒度低下の判定
III.アーチファクトの判別
IV.背景活動の判定
非突発性異常
I.非突発性異常の大雑把な判読
II.徐波の判読
III.代表的な徐波の判読(間欠的律動的徐波)
突発性異常
I.てんかん発作と脳波
II.てんかん焦点の決定
III.正常亜型(normal variants)の判定
IV.てんかんの発作型と脳波の関係〔てんかん新分類(2017)〕
V.てんかん焦点の決定
第3章 応用(実際の脳波の判読)/動画付
正常脳波
I.背景活動の判読
II.過呼吸賦活
III.睡眠脳波
IV.光刺激
V.総合判定
VI.臨床との相関
軽度異常脳波
I.背景活動の判読
II.過呼吸賦活
III.睡眠脳波
IV.光刺激
V.総合判定
VI.臨床との相関
中等度異常脳波(その1)
I.背景活動の判読
II.過呼吸賦活
III.睡眠脳波
IV.光刺激
V.総合判定
VI.臨床との相関
中等度異常脳波(その2)
I.背景活動の判読
II.過呼吸賦活
III.睡眠脳波
IV.光刺激
V.総合判定
VI.臨床所見との相関
中等度異常脳波(その3)
I.背景活動の判読
II.過呼吸賦活
III.睡眠脳波
IV.光刺激
V.総合判定
VI.臨床との相関
中等度異常脳波(その4)
I.背景活動の判読
II.過呼吸賦活
III.睡眠脳波
IV.光刺激
V.総合判定
VI.臨床との相関
高度異常脳波(その1)
I.背景活動の判読
II.音刺激
III.痛み刺激
IV.光刺激
V.総合判定
VI.臨床との相関
高度異常脳波(その2)
I.背景活動の判読
II.音刺激
III.痛み刺激
IV.光刺激
V.総合判定
VI.臨床との相関
第4章 良い爺〔いいじい(EEG)〕さんのQ&A
Q1:なぜ、判定に時間とテクニックが必要な双極導出法で判読しなければならないのですか?
Q2:それでは、双極導出法だけで脳波を判読すれば、基準電極導出法は不要ということになり
ませんか?
Q3:脳波の判読技術をスキルアップするためには、どうすれば良いでしょうか?
Q4:脳波を丁寧に見ていると、結構突発性異常のような波をたくさん見つけてしまい、全部の脳波が異常に見えてきてしまいます。どのように判定すればいいのでしょうか?
Q5:「健常者でもてんかん型の異常が出る」といわれると、ますますわからなくなってきました。いったいどこまでが正常で、どこまでが病的なのでしょうか?
Q6:てんかん発作の診断で、脳波所見と臨床所見の二つを兼ね合わせて考えるというのは、どういう意味でしょうか?
Q7:「てんかん発作を起こした人すべてに脳波異常が見られるわけではない」とのことですが、これは、どういう病態を意味しているのですか?
Q8:それではFIASはどのような症状を呈する症例で疑い、どのように検査を行って確定診断すれば良いのですか?
Q9:高齢初発のFIASは認知症と間違われやすいとのことですが、どのような臨床所見や脳波所見に注意して診察していけば良いのでしょうか?
Q10:意識レベルが低下している患者さんの診察を頼まれることが多いのですが、ベッドサイドで刺激を与えて反応を見ても、この患者さんが「意識障害」なのか、「傾眠状態」なのか、「正常の睡眠で深睡眠の状態」なのか迷うことがよくあります。どうやって鑑別すれば良いのでしょうか?
Q11:実際に意識障害の患者さんを診ていて困ることは、「この患者さんは今後良くなるのか、悪くなるのか。良くなった場合でも脳の機能に後遺症が残らないのか」などといった質問を、主治医や患者さんの家族から浴びせられることです。脳波検査も含めてどのように対処すれば良いのでしょうか?
Q12:認知症や軽微な意識障害の鑑別に脳波が有用とのことですが、それでは高次脳機能障害
の鑑別に脳波は有用でしょうか?
Q13:End of chain現象という言葉がよく出てきますが、これについてもう少し詳しく説明してください。
Q14:「耳朶の活性化」という言葉がよく出てきますが、これはどういうことですか?
参考文献
索引
おわりに
著者プロフィール
商品詳細
| 著者 | 古谷博和 |
|---|---|
| 出版社 | 金芳堂 |
| 発刊年 | 2025年01月 |
| ISBN | 978-4-7653-2024-5 |

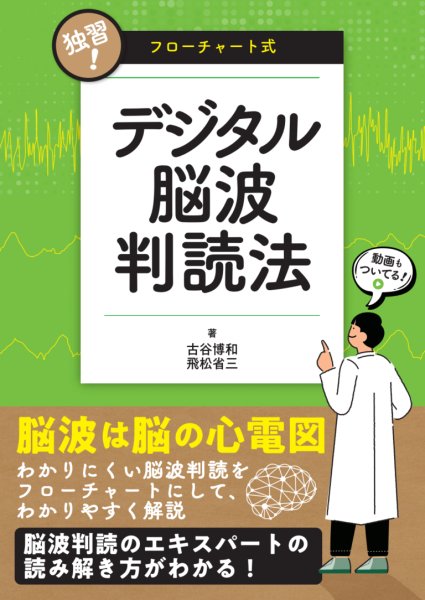

Facebookコメント